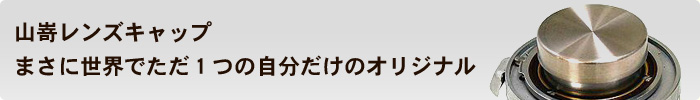
ご愛用のレンズに、山嵜(やまざき)ヘラ絞り製作所が熟練した金属加工技術により一点ずつ手製作する、特製キャップはいかがでしょうか。
山嵜ヘラ絞り製作所については月刊写真工業誌2003年6月号100~101ページに紹介記事が掲載されております。ここにその記事を転載いたしますので、ご一読いただければ幸いです。 ここで紹介されているとおり、ヘラ絞りの技術により一点ずつ製作いたしますので、様々な口径のキャップが製作可能です。古いカメラでレンズキャップが見つからず困っているというような場合、ぜひこの山嵜製キャップをご用命下さい。 また、山嵜製キャップは素材を純銀、純銅、真鍮、ステンレスなどからお客様の好みで選ぶことができます。特に高級なカメラには、純銀製鎚目入りがよく似合います。 製品の価格ですが、特注の場合レンズ先端外径42mmでは純銀の鎚目入りは18,000円(消費税別、以下同)、純銅あるいは真鍮の鎚目入りは10,000円です。また比較的数がでるもの、例えばプロミネント35のノクトンあるいはウルトロン用の前キャップはステンレス製で5,000円、リアキャップは3,000円といったようにお安くなっています。 価格については材質やサイズ、型の有無により変動いたしますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。
月刊写真工業誌(2003年6月号100~101ページ)より紹介記事を転載
「へら絞りは、とにかく重労働です。夏の暑い時期だと一日仕事をすると、体重が1kg以上も減ることがあるんですよ」
旋盤などの機械や道具が並ぶ作業場で笑いながら話し始めたのは、へら絞り加工で、レンズキャップや、修理用の工具を作っている山嵜省一さんだ。山嵜さんは、早田カメラでレンズ修理の手ほどきを受けたというほどのカメラ好きで、もちろん自らクラシックカメラの修理をこなし、モノクロの焼き付けまで楽しんでいる。本誌でもカメラやレンズの描写について健筆をふるっている。
「へら絞りというのは、簡単にいうと金属山寺事板を回転させて、塑性、成形させていく方法のことです。円形の材料を金型に当てて固定し、それを向転させながら、へらやローラーを使用して、密着させるように材料を成形していきます。プレスだと雄、雌両方の金型が必要で、高価になってしまいますが、へら絞りの場合は、雄型だけで製作が可能ですので、コストが低く抑えられます。材料が柔らかいものであれば、木型でもへら絞り加工が可能ですから、多品種少量生産には、おあつらえ向きの加工方法なんですよ」
へら絞りという名前を開いてもピンとこないだろうが、アルミなどの丸い照明器具、たとえば、Zライトのお椀の部分や台所で使うレンジフードの微妙なアールがついたダクト整流部分、そして、銅製の鍋やフライパンなど、たいていは一家にかならず1つは、へら絞り加工の製品があるはずだ。
「回転している金属をてこの原理を利用して、へら型に押さえつけていくんです。小さいものや鋼などの柔らかいものならそれほど力はいらないですが、直径1m以上で、ステンレスなどの硬い素材のものだと、かなりたいへんです。気を抜くと跳ねとばされてしまいますからね」
山嵜さんのへら絞り加工技術は、父君の寅七さん直伝だ。賓七さんは、新潟で、銅器作りの家に生まれるが、金属加工技術の新たな可能性を求めて、戦前にへら絞り加工技術を2年かけて修得。戦後は手術用の照明灯などの加工に腕をふるっていたそうだ。1953(昭和28)年に現在の葛飾区四つ木に移り、その後は、省一さんとともに、親子でへら絞り加工技術を駆使してさまざまな製品を作ってきた。
「へら絞りで、カメラ関係のものを作ったのは、修理工具が最初ですね。浅草の早田カメラに出入りするようになって、クラシックカメラの修理にも興味をもつようになったんです。自分でやってみるといろいろな工具が欲しくなってくる。エルマーやズミクロンの沈胴レンズの抑えリングを外すのに皆さんピンセットなどで苦労して、あげくのはてに傷をつけちゃう。それならと、早田さんと相談してへら絞りで作ったのです。あれほど苦労したリングがすばっと外れる。M型のクランクに隠れているカバー押さえのリングを外す工具なども作りましたね」
製作時のコストがあまりかからない、へら絞りだからこそ、こういった小回りのきく工具なども作ることができる。もちろん精度を出すためには、経験に裏打ちされた高度な技術が必要なのはいうまでもない。
「このレンズキャップは、まずは自分が欲しくて作りました。ライカの純正もいいのですが、もっとずっしりとした自分だけのキャップが欲しかったんです。 それで鋼で作って、人に見せたら皆が欲しがりましてね。それから欲しい人にお譲りするようになったんです。鋼の他にも真鎗や銀などでも作ります。大きさもズミクロンやエルマーはもちろん、サイズをいっていただければ、製作可能です。金属の表面にはなにも処理を施しておりませんので、使い込んでいくと酸化して、いい色がついてくるんです」
酸化するといっても1つ1つ微妙に色の付き方が違う。山嵜さんのレンズキャップは、まさに世界でただ1つの自分だけのオリジナルだといえよう。さらにこのレンズキャップには魅力がある。寅七さんと省一さん親子の合作だというのだ。
「僕が、へら絞りで形を作り、父がそれに鎚目加工を施します。鎚目加工というのは、金属の表面に金鎚で1つ1つ、目を付けていくものです。目の大きさを一定に保つためには、金属の材質や角度、位置によって叩き方を微妙に加減しなければなりません。この鎚目を付ける作業は、いまでも親父にはかないません。現在89歳ですが、まだまだ現役でがんばってもらわないとね(笑)」
へら絞りを戦前の昭和15、6年ごろに寅七さんが修得し、さらにその高度な技術を省一さんが受け継ぎ、研鋸してきた。 「へら絞りは、機械はなにもしてくれません。ただ金属が回転しているだけです。つまり金属という素材からへらやローラーを伝わってくる感触だけを頼りに形を作り出す作業です。1回1回が勝負であり、これからも毎日が修行ですね」
この親子合作のレンズキャップには、60年以上に及ぶ、へら絞りと2人の職人との格闘の歴史が刻み込まれている。




